ネットで話題になっていたので読んでみた。長年、母からの教育虐待を受けていた娘が母を殺害して遺体を切断、遺棄した事件(滋賀医科大学生母親殺害事件)を取材したノンフィクション。
刑が確定して服役している娘への面会や手紙のやりとりを経て、その内容をまとめたもの。
娘を医師にしたいという母の希望を叶えるため、医大を受験して9浪、その後に看護学部に入り、卒業後は手術室の看護師になりたかったものの、助産師の学校に入ることを強要され、その受験で落ちた直後に母を殺害。殺害に至るまでの経過も含めて、衝撃的な事件。そして、報道される記事だけではわからない、事件へ至るまでの長年の母と娘と家族の物語。
母と娘の話ではあるけれど、母は亡くなっているので、その主張を聞くことはできない。ここに書かれているのは、娘から見た母の姿。殺害後にSNSに「モンスターを倒した」と投稿したように、娘にとって母は「モンスター」だった。経緯を見ても、たしかに、モンスターとしか表現できないような、娘への異常な執着、身体的、精神的な束縛。同情する面は多々ある。
では、この事件を防ぐ手立てはなかったのか、と考える。事件は起こるべくして起こったのか、必然だったのか。
たしかに、母は異常だったけれど、ほぼ別居状態とはいえ、金銭的な面で生活を支えていた父(娘との関係も悪くなかった)、海外に住む祖母(母の母)も裕福で、折に触れて金銭の援助をしたり、手紙などのやりとりもあった。
娘は母に進路を強要されていたものの、予備校や大学に通ったり、アルバイトをしたりして、外部との接触や社会経験がまったくなかったわけではない。事件当時は30代に入っていて、判断が未熟な子どもでもない。実際に看護学科には首席で入学したというから、医大に落ちていたとはいえ、学力が低かったわけでもなかったと思う。
大学で看護師の資格を取り、母の殺害後も、それが発覚して逮捕されるまでの数ヶ月、看護師として働いていた。母を殺害せずに、外部に助けを求めたり、自立したりする道もあったのではないか。それでもどこに逃げても母が追ってくると思ったのかもしれない。いままでの母の行動を考えると、実際、そうしたかもしれない。
それでも、殺害して、遺体が見つからなかったとしても、人間ひとりが消えたらそれを隠し通すのは難しい。母が生きているように装って、母の友人などと母の振りをしてLINEのやりとりをしていた娘。それを、いつまで続けるつもりだったのだろう。
事件後、父や祖母も親身に娘の身を案じている。殺人犯として縁を切るわけでもなく、物資などの差し入れ、面会など、積極的に支援している。こんな人たちが周りにいたのに、なぜ、母娘のゆがんだ関係を正せなかったのか、娘を、母を、救い出せなかったのか、と歯がゆい。
母と娘、両方とも、被害者で加害者。どちらも救う方法が、きっとあったと思う。そう思えるのも、この本の内容が、娘の心の内を読み解き、事件の核心に迫ったものだったから。一審でかたくなに殺害を否認(母は自殺と主張)した娘が、控訴審で殺害を認めた経緯も興味深かった。母とのゆがんだ関係からの人間不信が、裁判官の説諭や父の支援を通して少しずつ氷解していく様子に、救いを感じる。
(電子書籍で読了)
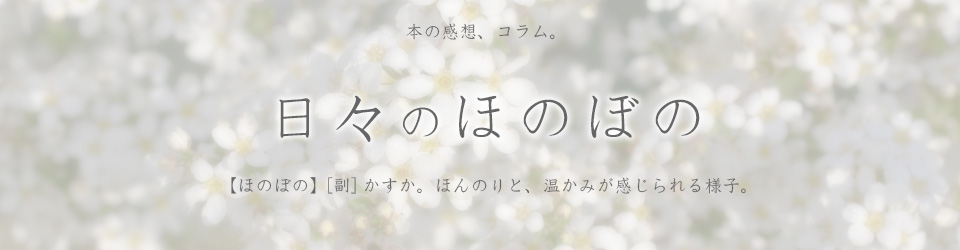

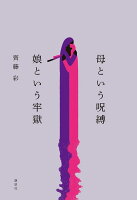



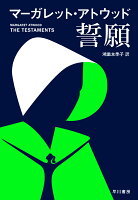
 RSS - 投稿
RSS - 投稿